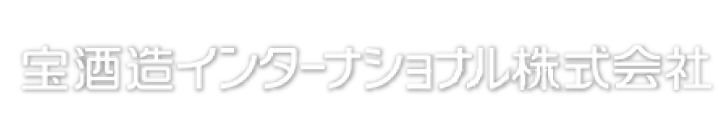

ABC’s of Sake
日本酒の知識
日本酒について
About Sake
日本の法律では、米と米麹と水などで醸造したお酒を清酒と呼びます。清酒の中でも、原材料と醸造地が日本であるものを「日本酒」と呼びます。国税庁より特定の産地名を名乗ることができる地理的表示としての認可を受けています。

日本人の主食である米と水から造りだされる日本酒は、長い間受け継がれてきた日本の文化の一つです。田んぼで育てられた米は良水で仕込まれ、長い時間をかけて蔵で醸しだされ、やがて日本酒に生まれ変わります。米の品種や製法によって、様々な香りや味わいが生まれ、四季折々の旬の食材との相性や、飲む温度で楽しめるお酒です。

酒米について
About Sake Rice
酒造好適米
日本酒造りに使用されるお米「酒米」の中でも、米の中心部に心白があり、酒造りに適した米を「酒造好適米」といいます。精米しても心白がきれいに残り、雑味のない酒が造れます。栽培に非常に手間がかかり、育てにくい貴重なお米であり、酒を醸すために大切に育てられた米です。

山田錦
酒造好適米の中でも「酒米の王様」と呼ばれている米の品種です。 心白が大きく、たんぱく質が少ない、吸水率、消化性が良いなど酒造りのすべての工程で優れた性質をもっています。香り高く、ふくらみのある味わいを楽しめるお酒に仕上がります。
五百万石
米どころ新潟県の米生産量が五百万石(約75万t)を突破したことを記念して命名された酒米です。くせのないすっきりとした味わいのお酒に仕上がります。飽きのこない落ち着いた味わいが多く、食事に合わせて楽しめます。
精米歩合
玄米の表層部を削り、残った米の割合を指す数値が精米歩合です。食用米の精米歩合は約90%といわれていますが、日本酒造りに使われるお米の精米歩合は、70%前後が一般的です。精米歩合60%とは、4割ほど米を磨いたということになります。精米歩合の低い、よく磨いた米ほど、香り高くクリアな味わいの日本酒に、精米歩合が高いと、香りは抑えめで、米の旨みを特長とした日本酒に仕上がるなど、精米歩合は日本酒の香りや味わいに特長を与えます。

味わいの指標
Flavor Indicators
日本酒度
日本酒の比重を表すための指標です。日本酒に含まれる糖分などが多いとマイナスになり、少ないとプラスになります。日本酒の味わいの甘辛を判断する目安になります。
酸度
日本酒に含まれる酸の量を表す指標です。酸は日本酒のキレを生み出すため、酸度が高いと比較的辛口の日本酒になると言われています。
酒造りについて
About Sake Brewing
仕込み水
日本酒の製造過程で使われる水が仕込み水。水は、日本酒の約80%を占めている成分で、どんな水を使うかで日本酒の仕上がりに大きな影響を与えます。硬水を使った日本酒は輪郭のはっきりした独特のキレがあり、軟水を使った日本酒はまろやかな口当たりに仕上がります。日本酒造りに使われている硬水として有名なのが、兵庫・灘の宮水。軟水として有名なのが、京都・伏見の伏水です。

宮水みやみず
宮水は、麹や酵母の成長を促すミネラルを適度に含む硬水です。酒の着色や味や香りの劣化の原因となる鉄分がほとんどなく、この良質な水が「灘酒」の名声につながったとも言われています。
伏水ふしみず
伏水は、適度なミネラル分を含む軟水です。京都伏見は「伏水」とも書かれるほど、質の良い天然の伏流水が豊富な土地で、日本を代表する酒どころとなった大きな要因と言われています。
麹こうじ
蒸米に麹菌を生やしたもので、デンプンを糖化し、米のたんぱく質をアミノ酸に変化させるため、日本酒の旨みを引き出します。麹は酒質をかたち作る基礎となります。
醪もろみ
醪とは、酒母と麹、蒸米、水を加えたもので、発酵中のものをさし、日本酒の前段階のものです。醪をこして製品化したものが日本酒です。
酒母しゅぼ
醪におけるアルコールの生成を行う酵母を育成するためのものです。雑菌の生成を抑えて酵母を純粋に増殖させます。酒母は文字通り「酒の母」ともいうべき、発酵の主役となる大切なものです。
酵母こうぼ
日本酒は発酵食品の一つです。日本酒造りに使用される酵母は「清酒酵母」と呼ばれます。目指す味わいや香りによって、酵母の種類を使い分けています。蔵で長年受け継がれている、蔵付き酵母や独自に開発した酵母などで、様々な特長をもった香り、味わいの日本酒が生まれます。

製法について
Sake Brewing Methods
生酛造りきもとづくり
酵母や乳酸菌などの働きを巧みに利用して手間と時間をかけた、昔ながらの伝統的な製法です。お米の旨みを強く引き出す製法で、しっかりとした濃厚な口当たりで、奥行きのある深い味わいに仕上がります。

袋吊り
醪を入れた酒袋を吊るし、自然にしたたり落ちるお酒を丁寧に搾り取る製法です。自然の重力によって搾り出すため、非常に手間のかかる搾り方と言われています。あまり日本酒を搾り取れないため、特別な日本酒を造るときに採用される製法です。ゆっくりと優しく搾り出すため、上品な香り、味わいに仕上がります。

生一本きいっぽん
単一の製造場だけで醸造し、製品化された純米酒です。
無濾過
無濾過とは、濾過をおこなっていない日本酒で、お米の味わいがしっかりと感じられるお酒です。品質管理が難しく、元々は酒蔵でしか飲めないお酒でしたが、近年は市場にも流通するようになりました。濾過したお酒と比べると味や風味の輪郭がくっきりしており、よく冷やしたり、ロックで飲むと、その独特の味わいが楽しめます。
原酒
醸造したままの日本酒です。一般的な日本酒のアルコール度数は15度前後ですが、原酒のアルコール度数は20度前後の高いものが多いです。しっかりとした飲み口で、旨みや香りが凝縮された、お酒本来の濃厚な香りと味わいが特長です。味わいが濃厚なため、日本酒ならではの旨み、酸味が薄まらず、日本酒カクテルのベースとしてもおいしく楽しめます。
生酒
加熱処理(火入れ)を行わず、生の状態で出荷される日本酒です。火入れをしないため、爽やかで、みずみずしく、フレッシュな風味が特長です。しぼりたての新鮮な香り・味わいが楽しめる日本酒です。よく冷すことでフレッシュ感が増します。
生貯蔵酒
生のまま貯蔵し、出荷前に一度、加熱処理(火入れ)を行うのが生貯蔵酒です。すっきりとした飲み口でイキイキとしたしぼりたての風味とともに、生の状態で貯蔵する時間が生酒に比べ長いため、お米のまろやかな風味も楽しめます。氷を入れたオン・ザ・ロックで爽快感が高まります。

日本酒の種類
Types of Sake
特定名称酒とは
お米の玄米規格、精米歩合や醸造アルコールの使用量といった所定の要件を満たした「特定名称」を表示できる清酒の呼称です。 ※特定名称:吟醸、大吟醸、純米、純米吟醸、純米大吟醸、特別純米、本醸造、特別本醸造
純米酒
米と米麹、水のみで、醸造アルコールは添加しない日本酒です。米の旨みや甘み、コクのある味わいなど、米本来の味わいを感じやすく、食事にも合わせやすいのが特長です。
特別純米酒
精米歩合が60%以下、あるいは特別な醸造方法による純米酒。精米歩合、醸造方法の違いから、様々な香り・味わいの日本酒になります。
純米吟醸酒
原料は純米酒と同じですが、精米歩合は60%以下。よく磨いたお米を長期低温発酵させる「吟醸造り」の日本酒です。「吟醸香」と呼ばれる香りと、純米酒ならではの米の旨みや甘みやコクがほどよく、様々な料理に合わせやすい味わいが特長です。
純米大吟醸酒
原料や「吟醸造り」の製法は純米吟醸酒と同じですが、精米歩合は50%以下。米を半分以上丁寧に磨き上げる、贅沢な造りの日本酒です。「吟醸香」はより一層華やかに広がり、米の旨みや甘み、コクがありながらもすっきりした味わいが特長です。
吟醸酒
米・米麹・水・醸造アルコールが原料で、精米歩合は60%以下。よく磨いたお米を長期低温発酵させる「吟醸造り」の日本酒です。「吟醸香」と呼ばれる、フルーティで華やかな香りが特長です。
大吟醸酒
原料や「吟醸造り」の製法は吟醸酒と同じですが、精米歩合は50%以下。米を半分以上丁寧に磨き上げる、贅沢な造りの日本酒です。「吟醸香」と呼ばれる、フルーティで華やかな香りが、より豊かで、雑味のない味わいが特長です。
本醸造酒
米・米麹・水・醸造アルコールを原料とする日本酒。精米歩合は70%以下。醸造アルコールを添加することにより、バランスの良い味わいに仕上がる日本酒です。濃醇さを残しながら、軽快さを持ち合わせた、すっきりとした口当たりが特長です。
特別本醸造酒
精米歩合が60%以下、あるいは特別な醸造方法による本醸造酒。米をよく磨くこと、あるいは特別な醸造方法により、通常の本醸造酒よりも繊細な味わいが特長です。




| タイプ | 特定名称酒 | 原料 | 精米歩合 |
|---|---|---|---|
| 純米酒 | 純米酒 | 米・米麹 | 規定なし |
| 特別純米酒 | 米・米麹 | 60%以下または特別な醸造方法 | |
| 純米吟醸酒 | 米・米麹 | 60%以下 | |
| 純米大吟醸酒 | 米・米麹 | 50%以下 | |
| 吟醸酒 | 吟醸酒 | 米・米麹・醸造用アルコール | 60%以下 |
| 大吟醸酒 | 米・米麹・醸造用アルコール | 50%以下 | |
| 本醸造酒 | 本醸造酒 | 米・米麹・醸造用アルコール | 70%以下 |
| 特別本醸造酒 | 米・米麹・醸造用アルコール | 60%以下または特別な醸造方法 |
醸造アルコールとは
吟醸酒、本醸造酒、普通酒を造る工程で添加する、純度の高いアルコールです。醸造アルコールの添加は、軽快な味わいや日本酒の香りを引き出す効果があります。
日本酒の楽しみ方
How to Enjoy Sake
お酒を飲む温度
日本酒は温度によって香りや味わいが多彩に変化するお酒です。温めたほうがおいしく飲めるお酒や冷やすほうがおいしく飲めるお酒もあります。日本酒は温めるほど香りや味わいが立ち、冷やせば冷やすほどにすっきりと口当たり良く、飲みやすくなります。飲むときの気分やシーン、季節によって、飲み方も温めて、または冷やしてと温度帯を変えて楽しめることが日本酒の魅力です。日本では季節や食事に合わせた、日本酒の飲み方を楽しむという文化があります。
| 摂氏(℃) | 華氏(℉) | 呼び方 | |
|---|---|---|---|
| 55 | 131 | とびきり燗 | Tobikiri-kan |
| 50 | 122 | 熱燗 | Atsu-kan |
| 45 | 113 | 上燗 | Jo-kan |
| 40 | 104 | ぬる燗 | Nuru-kan |
| 35 | 95 | 人肌燗 | Hitohada-kan |
| 30 | 86 | 日向(ひなた)燗 | Hinata-kan |
| 25 | 77 | 室温 | Shitsu-on |
| 20 | 68 | ||
| 15 | 59 | 涼冷え | Suzu-hie |
| 10 | 50 | 花冷え | Hana-hie |
| 5 | 41 | 雪冷え | Yuki-hie |




日本酒にまつわる風習
Customs Related to Sake
鏡開き
古くから清酒の樽のふたを、まるくて平らな形から「鏡」と呼んでおり、そこから樽のふたを割って、酒をみんなで飲み交わすことを鏡開きと呼んでいます。鏡開きには鏡を開くことにより運を開くという意味があり、縁起が良いため、現在でもさまざまな行事で行われています。

お正月の風習
古来より、新たな1年の始まりを迎えられた感謝と、また1年健康に暮らせるようにとの祈りを神に捧げてお供えした、そのお下がりである日本酒や料理をいただく、という風習が受け継がれています。



